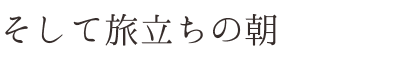クロスは走っていた。
今日は旅立ちの日。朝から、すでに飛び立った者たちも少なくはない。
自分ももう出立しないといけない時なのだが、それよりも大切な人の元へ向かうのが優先された。
息を乱し、その部屋に辿り着くのは早かった。
「エステル!」
扉を勢いよく開けると、まず目に入ったのは眉間にしわを寄せている医師の姿だった。
「クロス様、ここではお静かに願います」
もっともな言い分だ。慌てて、しかもノックもせずに部屋に入ってきてしまった。
「あ、ああ、すまない……」
「慌てるお気持ちも分からなくはないですが、ここは女性の部屋であることもお忘れなきよう」
医師の言葉は存外厳しい。
クロスは何も返すことができずに沈黙を保った。
「それと、エステル様。御身をお大事になさってくださいね。それでは私はこれで失礼します」
数枚の紙を抱えて、医師は部屋を後にした。そこに残されたのはクロスと、部屋の主であるエステルだ。
エステルは彼の来訪に驚き、目を丸くしていた。けれどその顔はどこか疲れきっていて、やつれているようにも見えた。
「クロス? どうしてここへ……」
エステルはベッドに入り、上体を起こしていた。少し辛いのか、壁にもたれ掛かっている。
クロスは彼女の元へ足早に近づくと、彼女の手を取った。
「お前が倒れたと聞いたから、急いで来た」
「そう、だったの……今日が旅立ちなのに、ごめんなさい」
いつも笑顔でいる彼女の姿が当たり前だったのに、今は痛みに耐えているような、苦痛を押さえているような表情をしていた。
クロスはそんな彼女を介抱するように、背中に手を添える。横になれば多少体も落ち着くはずだ。
「あまり喋るな。体に障る」
けれど、彼女は横になろうとはしない。クロスとも視線を合わせずに、ただ、自分の手を見つめていた。
「もう、私の体は無理かもしれない」
突然、彼女がそう口火を切った。
クロスは愕然とし、感情がたかぶっていくのが分かった。
「そんなこと言うな」
「病が私の体を蝕んでいくのが分かるの。もう、私は」
彼女の言葉を遮るようにクロスは抱き寄せた。そんな言葉は聞きたくない。
「頼むから、それ以上何も言わないでくれ……っ!」
「……」
彼女の体が、病に侵されているのは知っていた。けれども、こんなにも酷いものだとは気付きもしなかった。
いつもは春の日差しの中、咲き乱れる花のように麗しい彼女が、こんなにも弱ってしまうなんて。
クロスはなんと言葉をかけていいものか分からず、ただ、ただ彼女が離れてしまわないように抱きしめることしかできなかった。
「……ねぇ、クロス。私、お願いがあるの」
聞いてくれる? というエステルの声に、クロスはしぶしぶといった感じで彼女を腕の中から解放した。
「あぁ、何だ?」
泣き顔にも似た笑顔で、彼女は言う。
「私の娘を、守って」
「……あの子、か」
娘、という言葉にピンときたクロスは、その少女の姿を脳裏に思い浮かべた。遠目からしか見たことは無いが、彼女は、エステルと同じ緑色の瞳をしていた。
「あの子には辛すぎる……私のようになってほしくないの」
ぽたぽたと溢れでる涙を拭うこともできずに、エステルはそう呟いた。彼女の苦しみを、クロスは感じることはできても全てを理解することはできない。
それでも、彼女の懇願を果たすことで重荷を消しされるのならば、喜んで受けよう。
「……分かった」
「ありがとう、クロス」
彼の是という答えに、エステルは笑みを浮かべた。
「あ、あとね。もう一つわがまま言って良い……?」
□ ■ □
「――――急に来て申し訳ない」
「ロスト=フィア神?」
音もなく、書斎に姿を現した天空神を見てアーヴィンは驚いた。
今日は旅立ちの日。天空神は天界より〈渡り鳥〉たちを見送るのだと思っていたのだが。
「どうしたのですか?」
「いや、風の便りでな。……唄姫が倒れたそうだな」
天空神の言葉に、アーヴィンは納得した。そういえば彼はいたく唄姫であるエステルを気にかけていた。
……もしかして、気にかけていたのは、このことがあるかもしれないということを危惧していたからなのだろうか。
「見舞いにでも行こうかと思ってな。……だが、まだ行けぬようなので、お前の方に顔を出しに来たという訳だ」
「あぁ、今はクロスが行っているからな」
今日が旅立ちの日だというのに、どうしてこんなことが起こってしまったのだろう。運命という言葉をこれほど憎んでしまうのは、これで二回目だ。
アーヴィンは己の右翼を横目で見た。付け根がねじ曲がり、傷ついた翼。若干動かすことはできるが、空を飛ぶことはできなくなってしまった。これが一回目の憎しみ。
不幸というのはどうしてこうも連鎖してしまうのだろうか。
「……たぶん、もって五日くらいだろう」
天空神は静かに呟いた。
「エステル、のことですか」
「他に誰がいる。……あの病は、何年か体に居座り、巣を作り、そして、唐突に症状が現れる」
その病の原因も、治すための治療法も、未だ見つからない不治の病。
エステルはその病を抱えていた。クロスもアーヴィンも、彼女が何かしらの病気を抱えていることは知っていたが、まさかそれが不治の病だということは知らなかった。
「エステルは……?」
「彼女の症状は最悪だ。どうして倒れるまで気付かなかった? ……いや、気付かせなかったのか」
「そう、ですか……」
アーヴィンは悲しみに瞼を落とした。彼女にできることがもう何も残されていない。
後は彼女の命の灯火が消えていくのを、ただ待つだけ。
そこで、ふとアーヴィンの脳裏によぎるものがあった。
「……一つ、質問をしていいですか」
気がかりが、一つ。
「何だ」
「その病は、人から人へ移るものですか?」
確か、彼女には娘がいたはずだ。
もしもその娘にも同じ病が巣食っているのならば……。
「……五分の確率だな。それは我にも分からない」
天空神は首を横に振った。彼もまたそれを懸念しているのだろう。けれど、病までをも見通すことは神にもできない。こればかりは、どうしようもできない。
そうですか、とアーヴィンも短く返すことしかできなかった。
□ ■ □
ノエルは、白い煉瓦で作られた廊下を歩いていた。前を歩く男性はたぶんここの召使いなのだろう。白い布を頭から被っており、表情がよく見えない。
「……」
ここはあの白い建物の中。
つまり、族長や長老が住まう場所だ。そんな場所に、ノエルはなぜか呼ばれた。なぜ、呼ばれたのか詳しく説明されぬまま、ここまで至る。
一つ、二つ、と角を曲がり、廊下を歩いていくと突き当たりにぶつかった。かと思えばそこには一枚の扉がある。誰かの部屋だろうか、前を歩いていた男性がその扉の前で足を止めると、二回叩いた。
「族長、つれてきました」
「ありがとう。中に入ってくれ」
間髪入れずに返ってきた返事に、男性は何の躊躇いもなく扉を開けた。ゆっくりと開かれた部屋には、族長の姿。
「さあ、中へどうぞ」
男性に促されるままに、ノエルはその部屋へ足を踏み入れた。背後で小さな音を立てて扉が閉まる。
「よく来てくれた、ノエル」
「あの、私に何かご用ですか?」
呼ばれた理由がまだ分からない。
ノエルは率直にクロスへ問いかけると、彼は苦笑を浮かべた。その笑みが、どこか辛そうな色を帯びていることに、ノエルは気付いた。
「君に、彼女の看病をしてもらいたい」
彼女、という言葉にノエルはクロスの後ろに誰かがいることに気付いた。その人はベッドの上にいた。たわわな髪と、穏やかな瞳。顔がどこかやつれているように見えたが、その顔に見覚えがあったノエルは、驚きの表情を隠せなかった。
「エステルさん!? どうして……」
エステルは困ったような表情を浮かべていた。何かを言おうとして、代わりにクロスが口を開いた。
「彼女は病にかかっている。……今までは、俺が彼女を看病していたが、これからは無理だ。だから、俺に代わって彼女をみていてほしい」
「……どうして、私なんですか?」
この建物には召使いがいるはずだ。彼らはここに住まう人のお世話をすることが役目であり、彼女の世話も、召使いがやるはず。
「私に、ポエの話をしてもらいたいの」
その質問はクロスではなく、エステルが答えた。その声音はどこか疲れきっているようにも聞こえて、ノエルはまた疑問が増えていく。
そしてなにより、彼女の口から突然出てきた親友の名前に、ノエルは何度目かの驚きを見せた。
「ポエのことを? エステルさん……?」
疑問は膨らむばかりだ。
そんなノエルを見て、エステルはくすりと微笑んだ。
「あの子は……ポエは……私の、娘だから」
「……えっ!?」
彼女の突拍子もない発言に、ノエルは思わず声を上げた。それは一体、どういうことだ。
ポエ自身から、彼女の両親のことを聞いたことがある。「両親は旅に出ている」のだと。彼女は悲しげな瞳で、そう言ったのだ。
「すまない。時間が来てしまったので俺はこれで失礼するよ」
そう言うと、クロスは名残惜しげにエステルを見やり扉を開けた。
「クロス、わがままを聞いてくれてありがとう。気をつけて……いってらっしゃい」
彼が出ていく寸前、エステルはそう言った。掛け布をぎゅっと握りしめて、今にも泣き出してしまいそうな表情で、彼を見つめる。
「……ありがとう、エステル」
クロスは振り返らなかった。小さく、それこそエステルの耳に届くか届かないかの声でそう呟くと、部屋を出ていった。
ぱたん、と扉の閉まる音。
しばしの静寂の後、ノエルは口を開いた。
「あの、エステルさん。ポエの両親は……」
「旅に出ている、でしょう?」
ノエルの言葉を引き継ぐように、エステルは言った。それに対して頷くと、エステルはどこか寂しげな笑みを浮かべた。
「違うの」
そう言うエステルの瞳は、どこか遠くを見ているようで。
「あの子の親は私と、私の夫」
「……エステルさんと、族長の?」
それならば、なぜ今ポエとエステルは離れて暮らしているのだろうか。それに族長に子がいるとは知らなかった。
「いいえ。クロスではないわ」
だが、エステルはそれを否定した。
「……私は、前に別な方とお付き合いしていたの。とても優しくて、暖かい方。その方との間にできたのが、ポエ」
していた、という過去の形。
「……その方は?」
聞いてはいけないような気がして、それでも聞いておかなければいけないような気がした。矛盾した思いと、エステルの傷ついている表情が、心を揺さぶる。
「もう、随分前になるかしらね……私と同じ病で亡くなったわ」
それは遠い昔のようで、それでいて昨日のことのように鮮明に思い出せる。彼がベッドに横たわり、かすかな呼吸で、ずっと名を呼んでいたことを。そして、繰り返し謝罪の言葉を並べていたことを。
「ごめんな、エステル。お前を……置いていってしまう」
ずっとずっと、彼の手を握りしめていた。何かを言いたかった。それなのに何も言葉にできなくて、ただ溢れ出す涙をこぼれさせていた。
彼の命が消えて永久の眠りについても、体温が下がり冷たくなった手を、エステルはずっと握りしめていた。
「私は抜け殻のようになってしまったわ。……その一年後くらいに、クロスと出会ってね。彼のことを忘れたくて、クロスと結婚したの」
自分が壊れてしまわないようにと、全てを捨てて彼の元へ。
「ポエもまだ幼くて、母に預けていたの。そしたら、私のことも、夫のことも……忘れちゃった」
だから、母にお願いして「両親は旅に出ている」と嘘をついてもらった。そうすることが娘と自分を守ることに繋がると思っていた。……その当時は。
高ぶってきた感情を抑えるために、エステルは握り拳を作る。ぎゅっと強く、溢れ出てしまいそうな感情を痛みで抑制する。
「今考えても、クロスには悪いことをしてしまったと思うわ……」
当時はクロスにすがりつくしか、自分を保つことができなかった。情緒不安定になり、何度彼にすがり、時には罵倒を投げかけただろう。両手の指の数では足りないくらいほど繰り返したと思う。
そんな不安定な彼女を必死に支えてくれていた彼に、言葉に出すのは恥ずかしいけれどいつも感謝している。
「いろいろ、あったんですね……」
ノエルは彼女の悲しみを全て理解することはできない。
けれど、彼女がどれかけ悲しんで、苦しんだのか。その言葉から、その表情から察することはできた。
エステルは困ったような笑みを浮かべて、ノエルを見た。
「ええ。……ポエは、彼の忘れ形見」
でも、と一呼吸の間、エステルは言葉を区切る。
「今となっては悲しいわ。本当の親なのに偽っていかなければいけない……それに、もう、あの子と会うことも叶わない」
遅すぎる後悔を、何度すればいいのだろう。
これ以上の悲しみは、もう無いと思いたい。
「……だから、私にポエのことを話してくれる?」
きっと、親とはこういう生き物なのだろう。どんなに遠く離れようとも、子を大切に思う気持ちに変わりはない。
一度は手放したポエのことを、エステルは今もまだ苦しみに苛まれながらも守ろうとしている。
そんな彼女の姿に、ノエルは笑みを浮かべて、こくりと頷いた。
「……はい」
「ありがとう、ノエルちゃん」
そこで、やっとエステルは安心しきった朗らかな笑みを浮かべた。その笑顔の綺麗さに思わず見入ってしまったノエルは、はっとして口を開く。
「あ、あの『ちゃん』付けされるの、苦手なので、ノエルでいいですよ!」
慌てふためいて、何故かそんな言葉が出ていた。そんなことは別に今でなくてもいいことなのだが、出てしまったのだから仕方が無い。それに、『ちゃん』付けされるのは苦手だ。
「あら、そうなの? じゃあ今度からはノエルって呼ぶわね。でもアゼはノエルのことを『ちゃん』付けで呼ぶのにどうして?」
こてんと首を傾げるエステルに、ノエルも首を傾げた。聞きなれない、けれどどこかで聞いたことのある名前が頭に引っかかったのだ。
「アゼ……って、誰ですか?」
どこかで聞き覚えはあるはずなのだが、全く思い出せない。
ノエルの問いかけに、エステルは「あれ?」と小さく呟いた。直後、声を上げる。
「アゼイリアよ。ほら、手芸店の」
その名前に、ノエルも納得の声を上げた。『アゼイリア』で『アゼ』か。
「ああ! あ、あの人は何回言っても聞かないんですよっ!」
そう、あの人は人の話を聞いていない。聞いているかもしれないが、基本的に自分を中心に考えている節があるから、自分の都合の良いように言葉を解釈する。
だから、何度『ちゃん』付けを止めてもらおうとしても駄目なのだ。
苦虫を噛み潰したような表情を浮かべるノエルを見て、エステルは微笑んだ。
「ふふ、そうなんだ。大変ね、ノエルちゃん」
「そうなんですよ……って、ちゃんはやめてくださいってばー!」
□ ■ □
里の外れにある丘で、ポエは一人座っていた。何人もいた仲間たちは既に〈魂送り〉に飛び立ってしまい、ここに残っているのはもうポエだけである。
族長の言っていた暁の刻は、とうに過ぎていた。
「遅いなぁ……どうしたんだろう」
〈魂送り〉は二人ペアでやることになっていた。何か緊急の事態が起こったときに備えてのことらしいのだが、生憎とポエには理解できなかった。
けれど、一人で空を翔るよりは良いかもしれない。一人は、やっぱり寂しい。その寂しさを紛らわせることができるのならば、二人でやった方が良いと思う。
それにしても。
「あの看板に張り出されてた紙に書いてあった『クロス』って名前……一人しか知らないけど……まさか、ねぇ」
そう、ポエのペアとなる相手の名前は『クロス』という人らしかった。そして、その名前を一人だけ知っている。
「すまない。遅くなってしまった」
そう、この声の主だ……って、あれ?
いつの間にか傍に男の人が立っていた。急いで来たのだろう、若干息が上がっている。
だが、そんなことよりも何よりも。今目の前にいる人物が自分の良く知っている人で、驚きを隠せなかった。
彼は、まさしく族長であるクロスだった。
「……っえぇ!? 族長!」
やっぱりこの人だったのかという驚きと、何故この人なんだろうという二つの驚きが頭の中を駆け巡っている。口をぱくぱくと開閉するが言葉にならない。
そんなポエがおかしかったのか、クロスは苦笑いを浮かべた。
「これからよろしくな。あ、あと俺のことはクロスでいいからな」
「え、は、え……えぇーっ!?」