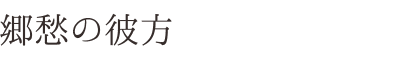どこか遠くで、誰かの声が聞こえた。
その瞬間、ポエは自分自身に違和感を覚えた。見えない何かに力を奪われていくような、虚脱感。
「ポエっ!」
クロスの叫びが耳に届く。
その声に答えようとして口を開いたが、声は音にならなかった。
自分の身に何が起こっているのか分からない。
空が遠く離れていく感覚を肌で感じながら、ポエは闇へ誘われてく。
――意識が途切れる寸前。
彼女は視界の片隅で、数多の白い鳥が羽ばたいていくのを見た気がした。
□ ■ □
ゆらゆらとたゆたう感覚に包まれている。周りには何もなく、ただ、自分だけが存在していた。どれくらいの時間そうしていたのかは分からないほどに、ただ流れに身を任せていた。
「……――! ――――!!」
誰かが声を張り上げていた。
まだぼやけた頭では音は言葉として成立しておらず、誰かが、大きな声を出しているということだけを理解していた。
「――! ――――――……ポエ!」
意識が、浮上していく。
それがクロスの声で、自分の名前を呼んでいることに気付いたのは、それから間もなくのこと。
ポエは重い瞼を持ち上げて、揺れる視界の中で彼を探した。数回瞬きをすると、鮮明になった世界の中に、沈痛な表情を浮かべる彼が見えた。
「……ク、ロスさん?」
彼の名前を口に出せば、ほっとした安堵の表情を浮かべた。それを見て、我知らずポエ自身も安堵の息を吐く。
「……あれ」
ふと、気づいた。いつの間にか、自分は大地の上に横になっていた。
鳥の鳴き声。獣の足音。風に揺れる木の葉のさざめき。色々な音が聞こえてくる。
辺りを見渡すと、どこかの樹林地なのだろう。背の高い木々に囲まれていて、上から差し込む日差しが暖かい。
ここはどこだろうか。
私は、一体何をしていたんだったか。
頭の中で疑問が巡る。急に黙り込んだポエに、クロスは訝しげに声をかけた。
「大丈夫か? どこか痛いところは?」
「あ……わたしは、だいじょうぶです」
痛いところはない。
それなのに、何故か声が震えた。
とにかく起きあがらなければ、と肘に力を込めて、上体を持ち上げる。背中に手を添えて支えてくれるクロスに感謝しながら、改めて彼と視線を合わせた。
「あの、ここは……」
疑問の言葉は、最後まで音にならなかった。
クロスを――正しくは、その背後を――見たポエは、驚きのあまり目を大きく見開いた。
「つ、翼が……っ!」
クロスの背中にあるはずの翼が、ない。
生まれ落ちた瞬間から背中にあったもの。
一対の純白は、彼ら有翼人の証でもある。
どうして、なぜ、という思いがぐるぐると脳内を駆け巡った。
「……急に、無くなったんだ」
ポエの驚きとは逆に、クロスはひどく落ち着いていた。
しかし、この現状に彼自身も戸惑っているようで、その顔は心なしか強張っていた。
「あの時のこと思い出せるか?」
「あのとき……」
あの時、というのは意識を失う前のことだろうか。突然の違和感。体から力が抜けていく虚脱感。次第に重くなっていく体。そのどれもが、今まで感じたことない出来事だ。
分からないと首を横に振れば、クロスは「そうだよな」と小声で言った。
「ポエ、君が意識を失った時」
彼はゆっくりと、ポエを――ポエの後ろを指差した。
「君の翼は突然……消えたんだ」
彼の言葉に、ポエは愕然とした。驚きのあまり思考が止まりかけて、そして、思い出した。
――そうだ。あの時、私は突然の浮遊感に襲われたのだ。どうしたらいいのかも分からずに、地面に向かって落ちていった。
あの時感じた浮遊感は、翼が無くなったからだったのか。
翼が無ければ、空を飛ぶ術ははない。
いつもと同じように、翼を動かそうと意識する。けれどそれは失敗に終わった。まるで回路が変わってしまったかのように、どうやって動かしていたのか、分からなくなっていた。
横目で後ろを見れば、そこに見慣れた白い翼は無い。
愕然としたポエの意識を戻したのは、困ったように、けれどほっとした様子のクロスの声だった。
「間に合ってよかったよ」
どうやら、気を失った直後にクロスに助けてもらったようだ。
そうでなければ、今頃、地面に叩きつけられて死んでいたはず。
感謝の言葉を告げると、ポエは彼の背後を見やった。見慣れたものがそこにはなく、どうしてか、心がざわついている。
「……クロスさんの、翼も?」
それならば、彼の翼が無いことにも納得がいく。
彼は「そうだ」と呟いた。
「君を抱えて地に降りようとした時に、俺の翼も消えたんだ」
「えっ、だ、だいじょうぶですかっ」
さらりと言われたことに、ポエは驚きを隠せなかった。もしかしたら、彼の方が傷を負ってしまったのでは。
「真下にあった木が衝撃を吸収してくれたみたいでな。ちょっと体は痛いが、問題はない」
そう言われても、心配は拭い去れない。
慌てて彼の手を取り、上から下まで怪我がないかを見る。特に、目立った外傷は無いようだ。
「見ての通り大丈夫だ」
ポエを安心させるためにでまかせを言ったのだと思ったが、どうやらそうではないらしい。
「…………そのようですね」
とりあえず一安心だ。まさか、こんな状況で怪我をしてしまっては治すに治せない。治癒の術を持ち合わせていたものの、漠然と、それは使えないと分かった。
何故だかは分からない。ただ本能とも呼ぶべきところで、様々なことを無意識のうちに理解している気がした。
「――――無事のようだな」
突然、声が降ってきた。しかし、その声の主の姿は見えない。
聞いたことのない声に、ポエは驚いてクロスの背後に隠れた。
「……この声は」
クロスにとって、その声は久しぶりに聞くものだった。世界に飛び立つ前。里の中で聞いた彼の声を、忘れるわけがない。
不自然な風が吹き荒れ、目の前に白く巨大な鳥が舞い降りてくる。
「久しぶりだな」
そう言った鳥は、瞬く間に人の姿をとった。
ふわりと風をまとって現れた彼は、あの里で出会った時の姿のままで、色素の薄い瞳を二人に向ける。
懐かしさがこみ上げてきて、クロスは思わず破顔した。
「ご無沙汰しております、ロスト=フィア神」
「……かみ、さま?」
ポエはクロスの後ろから顔を出して、彼の顔を見る。
「お主と
端正な顔には何の感情も浮かんでおらず、髪も瞳も衣装さえも薄い色彩に包まれている彼は、どこか儚い印象を受けた。
「うむ。まこと、エステルにそっくりだな」
じっとポエを見ていた天空神が、いきなりそんなことを言い出した。
「え?」
突然、何を言い出すのだろう。ポエは首を傾げた。エステルに似ていると言われたのは、この神で二人目だ。そんなにも似ているのだろうか。嬉しいような、なんだか微妙な気分になる。
「ロスト=フィア神!」
彼の言葉に反応したのはポエだけではなかった。目の前の彼は、何やら含みのある声で天空神に迫る。
「喚くな。多くは語らぬ」
クロスが声を荒げていることに疑問を抱きつつも、天空神はそれ以上そのことについて何か言うことは無かった。
だが、次に発した言葉は到底、理解できるものではなかった。
「ご苦労だった。翼が無くなったのは、君たちの〈宿命〉が終わったからだ」
――――彼の言葉の意味が理解できなかった。
「どういうことでしょう」
「君たちの〈渡り鳥〉の役目は終わった」
ロスト=フィア神の言葉に、変わらない表情に、クロスは苛立ちをつのらせる。
「翼は力の源。役目を終えた力は昇華する」
役目を、終えた。
それはつまり、この世界をさまよっていた魂を、天に送り届けることができたということだろうか。
「力は無限にあるものではない。使い続ければ、いつか果てるものだ」
〈渡り鳥〉たちはその使命を、〈宿命〉を背負って、小さな里から飛び出したのだ。
「君たちは長く保った方だ。数多の〈渡り鳥〉が力を使い果たし、そして翼を失った」
「……意味が、分かりません」
神の言葉に口を挟むのは得策ではないのだと知っていても、挟まずに入られなかった。
「私たちは、帰れないのですか」
クロスは呆然とした表情で囁いた。
かの神の言うことは、信じられないことばかりだ。
「君たちは、君たちの故郷へ帰ることはできない」
――役目を終えたのならば、生まれ故郷へと帰ることができると思っていた。
神の言葉に偽りはない。それはいつも真実で、そして無慈悲だった。
突然の告白に、そして意味を理解するのに十分の時間が必要だった。
そして、その意味を理解した時に、ポエは悲憤でどうにかなってしまいそうだった。
ぎゅっと服の裾を強く握りしめることで、爆発しそうな感情を抑える。爪が食い込む。その痛みが、悲しくもこれは現実だと教えていた。
「どうして……っ」
帰れないだなんて、聞いていない。
里を出た時は、今生の別れのように思った時もあった。ただ、世界を巡る内に、〈魂送り〉をしていく内に、一縷の望みをかけた。
〈魂送り〉が終われば、いつかきっと帰れるのだと思っていたのだ。
視界が揺れて、慌てて下を向いた。ともすれば熱いものが溢れてきそうになるのを必死にこらえる。
強く握りしめた手に、暖かい大きな手が触れた。はっとして顔を上げると、クロスが心配そうな表情でこちらを見ていた。
――はらり、と一筋の涙がこぼれた。
「大丈夫か」
なぜ、彼はそんなに落ち着いていられるのだろう。ポエには分からなかった。こんなにも感情がぐるぐると渦巻いている。
くるりと振り返り、ポエは天空神を睨みつけた。
憤りは、そのまま言葉として溢れた。
「あなたは神様なんでしょう!」
激情を抑え切れないまま、思っていた言葉が口にでる。それを見ていたクロスには、彼女の苦しみも、悲しみも、痛いほどに理解することができた。
――けれども、彼は神なのだ。
神は下界の者の思惑にはのらない。
「神様なら、なんとかしてよっ!」
「一度目の罪は赦された。二度目は赦されない」
ポエの悲痛な叫びを止めようとしたクロスよりも早く、彼女の声を止めたのは、そんな彼の言葉だった。
クロスははっとして天空神を見やる。
その表情はいつもと同じ感情のないものに見えて、それなのにどこか痛みをはらんでいるようにも見えた。
「……天空神?」
しかし、次に目を瞬いた時にはそれは消えていた。
今のは、気のせいだったのだろうか。
彼の言葉に、ポエも唖然としたまま固まっていた。
しばらくの間、彼らの間を静寂が包み込んだ。
誰もが口を閉ざしていたのを破ったのは、天空神だった。
「――今更だが、君たちには伝えなければいけなかったことなのだろうな」
どこかしんみりとした面持ちで、天空神は言葉を続けた。
「君たち〈渡り鳥〉の持つ翼には力がこめられている。力とは、即ち〈魂送り〉を成すための唄の力」
――――〈渡り鳥〉という存在が生まれる前。
ある地界の生き物は空に憧れ、遠くまで広がる澄み渡った蒼い色に心を惹かれた。
生き物は願った。
もっと空を近くでみたい。空を駆け巡りたい。
空を自由に舞う翼が欲しい、と。
幾年の時が過ぎ去ろうともその願いが無くなることはなく。その声をずっと聞いていたある天界の者は、その願いに応えることにした。
しかし、それはいけないことだった。
「天界に住まう者が地界の者に接触するのは、禁じられているのだ」
その禁を破った天界の者こそ、天空神ロスト=フィア。彼は神の力を使い、生き物に一対の純白に輝く翼を与えた。
しかし、その翼には神の力の一部が宿っていた。地界の者が天界の力を有することは、禁忌にも近い。
――そして、代償が生まれた。
地界の者が曲がりなりにも天界の力を持ってしまったのだから、代償が生まれてしまうのも道理というもの。
その力の代償こそ、彼らの運命を強制的に決めつけてしまった〈宿命〉である。
神の力は強大だ。
一部とはいえ、それは時として、己が身を滅ぼしてしまうほどに強い。
そこで天空神は考えた。神の力を使い続ければ、いつかはその力が無くなるのではないだろうかと。
そうして〈魂送り〉は生まれた。
彼らの持つ力を昇華させるためのもの。
力を言葉に、言葉を唄にして紡ぎ、〈魂〉を天界に送ると同時に力を昇華させる。
そして、力を全て使い果たすと〈渡り鳥〉は役目を終えるのだ。
――――翼という〈力の器〉を無くして。
理不尽な真実だと思った。だがそこでクロスは気付いた。
先ほど天空神が言った『一度目の罪』というのは。
どこか遠くを見ている天空神が小声で呟く。
「……どんな願いであっても、地界の者に力を使ってはいけなかった」
彼の神は悔いているのだろうか。
力を使ってしまったことを。
……代償が生まれてしまったことを。
「ロスト=フィア神……」
クロスが何事かを言う前に、天空神はそれを手で制した。
「過ぎてしまったことを、今更どうこう言うつもりはない」
淡々とした表情で、神は低く告げる。
「そして、今こうなってしまったことに、我は関与することは赦されない」
赦されるのは〈魂送り〉を伝えることと、直接手を出さないこと。それを歪めれば、さらなる
ならば、いっそ心を突き放してしまえばいい。一時の気まぐれで力を分け与えただけの存在だ。これからどうなろうと、天空神の知ったところではない。
――そう、ずっと思っていたはずだった。
脆く、弱く、頑是無い鳥。離れようとすれば逆に気にかけてしまう。心は情を生み、もう離れることはできないほど、天空神は彼らを――〈渡り鳥〉を、我が子のように愛していた。
今更、突き放すことなどできるわけがなかった。
「ロスト=フィア神」
ぽつり、と呟かれた少女の声が耳に届く。見れば、先程まで激情をはらんでいた瞳は落ち着いていて、いっそ哀れんでいるようにも見えた。
それがおかしく思えて、内心苦笑してしまう。
哀れむのは自分自身の方だろうに。
この少女は、本当に情に脆い。
だからこそ、できることなら救ってやりたいと思う。直接彼らに何かをすることはできないけれど、その手助けだけならば、あるいは。
――なればこそ、彼らは決断しなければいけない。
すっと表情が変わった天空神を見て、クロスもポエも身を固くした。
「君たちに問う」
押し殺したような低い声。
「翼を無くし、飛ぶこともできず。標を失い、故郷も分からず。それでも、帰れると思うのか?」
天空神の辛辣な言葉に、ポエは息を詰めた。
里から外の世界へ出ることができたのは翼があったからこそで。
力があったからこそ、外の世界でも生きていくことができた。
その力の源が翼であったのならば、その翼を無くした私たちは、これから生きていくことができるのだろうか。
沸き起こった不安はポエを飲み込み、足が、手が、震えた。
「それでも」
その声に、ポエは目の前にいる彼を見上げた。
大きい背中だ。里を出てから、そして、今日までずっと彼の後ろ姿を見続けてきた。
――彼は、不安ではないのだろうか。
ポエはそっと彼の手に触れる。クロスは振り返り、眼下にいる彼女を見ると、優しく微笑んだ。
その瞳が不安に揺れているのにポエは気付いた。
けれども、彼はすぐに前を向いてしまって声をかけることはできなかった。
クロスは、力強く彼を見返す。
「それでも俺は、俺の生まれた場所に帰る」
それが叶わないことだと知っていても、諦めることだけはしたくなかった。
その強い眼差しと意志のこもった強い言葉に、天空神は瞼を伏せる。
「……そうか」
〈渡り鳥〉の〈宿命〉は絶対で、変えることはできない。
はじまりもおわりも、全てが彼らに無慈悲で、残酷である。
それでも彼らが前を向いていくというのならば――
「ならば、最後に情けをやろう。我にできるのはここまでだ」
天空神が軽く腕を振りあげた瞬間、ポエは全身を何か暖かいものに包まれる感覚に陥った。それはクロスも同じだったようで、驚いた表情で天空神を見ている。
これは、無くしたはずの力。
だがそれはあまりにも弱々しく、これまでの力とは明らかに違っている気がした。
――けれど、希望が差し込んだ。
「往け、翼を無くした鳥よ」
彼は多くを語らず、ただ凪いだ眼差しだけを向けている。
いつの間にか、全身を包み込んでいた暖かいものは消え失せていた。
「願わくば、その儚くも強き願いが叶えられることを」
翼を無くした鳥は空を飛ぶことはできなくなってしまったけれど。
地につけた足はまだ動かせる。
「君たちに良き風が吹くことを祈っている」
くるりと背を向けた天空神は、瞬く間にその姿を巨大な鳥に変えて、大きく翼を打ちならした。頬を打ちつける風が痛い。ポエとクロスは庇うように両腕で顔を覆った。
「――――」
また何か聞こえた気がして、ポエは腕の隙間から先を見た。
舞い上がった巨鳥の瞳が、こちらを向いていた。視線が交わり、その一瞬後にはもう高い空の上にその姿はあった。
「……行っちゃいましたね」
顔を覆っていた両腕を下ろし、天空神が巻き起こした強風がやむ頃には、もう鳥の姿は見えなくなっていた。
「そうだな」
どこか寂しげな声が落ちる。
「……クロスさん」
どこまでも広い青空を見上げながら、ポエは彼の名前を呼んだ。
「ん?」
「…………本当に」
本当に、帰れると思いますか。
そう聞きたくて、けれども口に出してしまうのが怖くて、言葉にできない。
ポエのそんな心情を知ってか知らずか、クロスは困ったような表情を浮かべて、空を仰ぎ見た。
「……さぁな」
帰れないかもしれない。
……もしかしたら、帰れるかもしれない。
こればかりは、自分も、そして最後に情けをかけてくれた天空神さえも分からないだろう。
「でも、俺は帰るよ」
分からないからこそ、諦めてしまったら駄目だと思った。どんなに希望が小さくても、願いを叶えるために歩き続ければ、きっと。
「私も、帰ります。私の故郷に」
不安を抱く心を打ち消すように、強く、自分に言い聞かせるように言った。
クロスはそんな彼女を見て苦笑いし、ぽんと頭に手を乗せた。
「……とりあえず、ここから近い町に行くか」
「はい。がんばりましょう」
不安がないわけではない。
それでも、お互いがいればきっといろんな困難にも立ち向かえるような気がした。
歩きだした鳥たちの背中には空を自由に飛ぶ翼は無くなってしまった。
されど、彼らは立ち止まることなく、新たな一歩を踏み出した。
鳥は言葉をもって唄とする。
唄とは心と情を紡ぐ魂の音色。
その旋律は、今もまだどこかで唄い紡がれている。