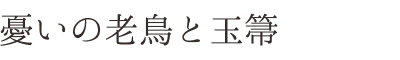「……ふう」
詰めていた息を吐き出すと、アーヴィンはペンを置いた。ずっと同じ姿勢をしていたからだろうか、肩が少し痛い。
「アーヴィン様、少々お休みになられてはいかがでしょう」
仕事の成り行きを見守っていた側仕えが声を上げる。先ほどからずっと何か言いたげな顔つきだったが、またそれか。
今日でその台詞を聞くのは何回目だろうか。
アーヴィンは彼に一瞬目をやったが、返答はしなかった。
「ここ数日あまりお休みになられてはいないですよね?」
「……あと少しで終わる」
そう答えると、側仕えはあからさまに不満そうな表情を浮かべた。アーヴィンはそれに気付かない振りをして、手元の羊皮紙に視線を落とす。
ここ数日、気持ちがざわついて落ち着いていられなかった。
理由は分かっているつもりだったが、かといって、それをどうにかできるとも思っていなかった。
ただ何かに没頭していれば、時が経てば、いつしか忘れてしまえる気がした。
けれども、そんな思惑とは裏腹に、ふとした瞬間にそれを思い出してしまう自分がいた。
「……アーヴィン様」
咎めるような声音が耳に届く。
仕方がない、と手元の羊皮紙からゆっくりと顔を上げた。呆れとも、苛立ちともとれる表情をしている側仕えを一瞥し、口を開いく。
「分かった、休む。……すまないが、しばらく一人にしてくれないか」
それは問いかけではなく、断言。
側仕えが何かを言おうとして開いた口は、しかし何の言葉も発せられず。
一文字に唇を結んだ彼は、一度深呼吸した。
「…………分かりました」
側仕えもアーヴィンのまとう空気を読んだのか、それとも別な何かを感じ取ったのか。そう答えるとそのまま踵を返して部屋を出ていった。
ぱたん、と小さく扉の閉まる音が耳に届く。
……自分以外誰もいなくなった部屋は、とても静かだ。
背もたれに体重をかけるとぎしり、と椅子が鳴った。体から力を抜き、ふう、と深く息を吐き出す。
「……」
目をつぶり、ただただ静かなその空間で時が過ぎるのを待つように、ひっそりと呼吸を繰り返した。
――それから、そんなに時間は経っていなかったように思える。もしかすると、結構な時間が経っていたのかもしれないが。
「長老、いらっしゃいますか」
うとうとと霞がかっていた意識が、扉の向こうからやってきた声に起こされる。
はっとして頭を振り、意識を覚醒させる。
机に転がっていたペンを持つと、アーヴィンは何事もなかったかのように扉の向こうへ声をかけた。
「はいれ」
小さなノックの音とともに「失礼します」と一人の男が部屋に入ってきた。確か、玄関の警護をしている者の一人だと認知していたが、なぜ彼がここにいるのだろう。
アーヴィンは首を傾げた。
「あの、ええと、お客様がお見えなのですが……」
妙に歯切れの悪い口調。
「客?」
アーヴィンは顎に手を添えて、今日の予定を思い返した。確か、今日は来客の予定は入っていなかったはずだ。約束も取り付けずに、急に来られても困るのだが……。
「今は立て込んでいて出られん。悪いが、後日改めるように伝えておいてくれ」
できれば、今度はちゃんと会う約束を取り付けてからで。
話はこれで終わりだろう、そう思っていたアーヴィンだったが今回は違った。
「え、えっと……」
いつもならば二つ返事ですぐに部屋を出ていく彼が、今回に限って妙に渋っている。もごもごと口の中で言葉を紡ぐものの、それが言葉になることはなく。
彼がそんな行動をとるのは初めてのことだったので、アーヴィンも思わず眉を寄せた。
言い淀んでいるのならば、はっきりと言ってしまえばいいものを。この男は一体何を悩んでいるのだろうか。
「なんだ。はっきりしたまえ」
その一言に意を決したのか、小難しい表情で召使いは口を開いた。
「天空神がお見えになられています」
それは、到底この場で出てくるような名前ではなく。
アーヴィンは持っていたペンを落とした。
□ ■ □
慌てて玄関へ向かうと、そこには困惑している召使いたちの姿。
そして、その真ん中に天空神の姿があった。
走っていくのはさすがに憚られたので、彼の姿が視界に入った時点で小走りに変える。
「――ロスト=フィア神」
彼の前まで来ると、乱れた息を整えて深々と頭を下げた。
「おお、遅かったな」
アーヴィンの姿を見て、天空神は小さく笑みを浮かべた。
「どうしてこちらに?」
いつもならば、この神はアーヴィンのいる部屋の窓から忽然と姿を現すというのに。
頭を上げながら問いかけると、天空神は何故か目をぱちくりさせていた。
おや、とアーヴィンは思う。彼にしては珍しい表情をしている。
物珍しげに彼を見ていると、その口から言い放たれた言葉に耳を疑った。
「ん? この間、お主が『次からはちゃんと玄関からお越しください』と言っていたであろう」
だから玄関から来てやったぞ。
胸を張ってそう言い放った神は、言いつけを守った子供のように見えて少々おかしかった。
――おかしかったのだが、それはそれ。これはこれ。
「…………」
アーヴィンは頭を抱えたくなった。
その台詞は確かに言った記憶がある。
だがしかし。まさか律儀に約束を覚えているとは思わなかった。
それも、それはただの口約束。人と人がするものであり、人と神が容易にしていいものでなければ、神が守る必要もないもの。
「…………」
唖然としていたアーヴィンは、気分を落ち着かせるために息を吐きだした。何度か呼吸を繰り返していると、気分も少しだけ落ち着いてきた。
……さて、ひとまず突然の神の出現に恐れおののいているこの場をどうにかしなければなるまい。
とりあえず、目の前にいる天空神をどこか部屋に連れていくべきだろう。
「皆が落ち着いて仕事ができませんので、奥の部屋へ行きましょう」
先程から召使いたちがそわそわしている。初めて見(まみ)えた神の姿に驚きを隠せないでいるのだろう。
ここにいては彼らの仕事の邪魔になってしまう。
アーヴィンの心境を知ってか知らずか、天空神はいつもの無表情で頷いた。
「そうだな」
それではこちらへ、とアーヴィンは歩き出す。一歩半の歩幅を空けて、天空神は彼の後をついていった。
自室まで足をのばすと、天空神と一緒についてきていた側仕えに人払いを命じる。彼は二つ返事で頷き、天空神に向き直って一礼をする。
そして、くるりと背を向けて来た道を戻っていった。
これで暫くは誰もこの部屋に近づかないだろう。
扉を開けて、天空神に中へ入るように促す。
「いつ来ても整っているな」
部屋の中を見渡しながら、天空神は言った。
「物が無いだけですよ」
そう答えながら、天空神の後に続いて室内に足を踏み入れる。
アーヴィン自身、物欲があまり無いことを自覚している。この部屋には必要最低限の物しかない。ほとんどが長年受け継がれてきた長老という立場上で必要な物である。
アーヴィンの持ち物といえるものは、一つだけしかなかった。
「花でも飾ったらどうだ? 少しは華やかになるだろう」
突然そんなことを言い出した天空神に、思わずうろんげな視線を送る。
「華を持たせてどうするんですか」
「あいつも好きだったろう」
思わず、アーヴィンは目を見開いた。
この神はいきなり何を言い出すのだろう。
あれやこれやと言い訳じみた言葉が脳裏を駆け巡り、何かを言わなければと口を開いたが言葉は何も出てこない。
しばらく悩んでいたものの、結局、アーヴィンは彼の言葉に首肯するしかなかった。
「…………そう、でしたな」
もう遠い昔に儚くなった彼女の――妻の記憶がよみがえる。
彼女は毎日部屋を訪れては、いつも違う花を飾っていた。色鮮やかな花をどこで手に入れてくるのか、ついに知ることはできなかったのだが。
それを密かに楽しみにしていたのは、自分だけの秘密だ。
懐かしい記憶を思い返していたアーヴィンは、耳に届いた咳払いの音にはっとする。
天空神が、意味ありげにこちらを見ていた。
「すみません」
「いや」
思わず、懐かしい思い出に浸ってしまった。
「それで、今日はいかがしましたか? まさかとは思いますが、昔話をしに来たわけではないでしょう」
天空神が椅子に座るのを確認しながら、机の向こう側にある自分の椅子へ向かう。
「少し気懸かりなことができてな」
アーヴィンは自分の椅子に座りながら、彼の言葉を聞いた瞬間、背筋が凍った。
――気懸かりとは、まさか。
「……〈渡り鳥〉たちに、彼らに、何かあったのですか?」
この里に暮らしていた者が〈渡り鳥〉として、避けられぬ〈宿命〉を背負って世界に飛び立ってから随分と経ってしまった。
何度、自身の持つ飛べなくなってしまった翼を悔やんだことだろう。
息子を守れたことに悔いは無い。
だが、その代償として空を飛ぶ術を失ってしまった。
そして、あの日守り抜いた息子は、あの時の自分と同じように〈魂送り〉をするために、世界へと飛び立っていってしまった。
「彼らは大丈夫だろう」
しかし、そんなアーヴィンの不安をよそに、天空神はけろっとした様子で答えた。
我知らず、彼に訝しげな視線を送る。
「……大丈夫、だと?」
是、と天空神は答えた。
「多くの〈魂〉は天に還りつつある。〈渡り鳥〉たちが唄を紡いでいるお陰でな」
……それは、良かった。
この小さき里で過ごしてきた彼らが、世界へと飛び立った時、心配がなかったわけではない。
外の世界は未知で溢れている。何が起こるか分からない。最悪、命を落としてしまうことだってあるだろう。
自分も、一歩間違えれば死んでいたかもしれなかったのだ。
だからこそ、この心配事が杞憂で終わればいいのにと、いつも願っている。
――しかし、神の言う『気懸かり』がこれではないというのなら、一体何なのだろう。
「ならば、貴方の気懸かりというのは……」
「ふむ。そんな大したことではない」
そう言いながら、彼は懐から小さな包みを取り出した。それをアーヴィンの前に差し出す。
「お主に」
眉一つ動かさず、顎をくいっと差し出された。
つまり、開けろということだろうか。
「これは……?」
しゅるり、と包みの口を縛っていた飾り紐を解く。今まで見たことがないこの鮮やかな色合いの紐は、きっと極上品なのだろう。これだけで相当の価値がありそうだ。
次いで、中身を覆っていた布を取っていく。
現れたのは、淡い青色の陶器――徳利だった。首の部分には濃い赤の紐が括られていて、先端には透明な丸い玉が通されている。
壊さぬようにと優しく首を持ち、軽く揺らしてみる。
ちゃぽん、と水音がした。
「酒だ。飲め」
短く、それでいて断固とした口調で彼は言った。
彼の言葉が急すぎて、その意味を理解するのに時間がかかった。至極真面目な顔をしている――とはいっても、常に無表情なのだが――天空神を、思わず見返した。
「…………勤務中に飲酒は、如何なものかと」
一体、何がどうして、この神は急に酒を持ってきたのだろう。意味が理解できずに、アーヴィンは戸惑うしかなかった。
そんな彼の心情を知ってか知らずか、天空神は何事もなかったかのように言葉を続ける。
「酒は酒だが、酔うほどの酒精は入っておらん。薬師神が作った薬酒だ」
酒精が入っているとか入っていないとか、そういう問題ではない。そう言おうとした時、彼が続けて言った言葉に違和感を覚えた。
「……薬酒?」
「うむ」
薬酒、とはつまり薬のことだろうか。
「私に?」
その問いかけに、天空神は憮然と頷いた。
ますます意味が分からない。
「何故、とお聞きしてもいいだろうか」
突然彼が現れた理由も、このようなものを持ってきた理由も皆目検討がつかない。
困惑しているアーヴィンの表情を見て、天空神は呆れた表情を隠そうともせずに呟く。
「やはり自分では気付かないものだな」
「……気付かない?」
「お主、かなり疲弊しているように見えるぞ」
その言葉にアーヴィンは動揺した。目を見開き、思わず天空神を見返す。
そんなことを言われるとは、思ってもいなかった。……彼自身、疲れを感じていることはあっても、それを表に出すようなことはしていなかったからだ。
まさか一目見ただけで見破られてしまうとは、感嘆せざるをえない。
しかし、天空神のどこか威圧的な言葉は、ずしりと重りのように心にのしかかっていた。
「気を張りすぎている。少しは休め」
なんと返答したものかと悩んでいる間に、優しい言葉をかけられてアーヴィンはますます思案に暮れた。
「…………」
返す言葉も見つからず、俯いて黙り込むしかない。
暫しの間。それをどう捉えたのか分からないが、天空神は溜息を吐いた。
「我が見て分かるほどに、お主は疲れきっている。我が分かるということは、普段近くにおる者たちも、当然、分かっているはずだ」
そんな彼の言葉に、ふと、アーヴィンはここ最近のことを思い返した。
部屋で仕事をしている時。用があって外出する時。側仕えや召使いたちが、なんとも言えぬ表情を浮かべていたのには気付いていた。その時はどうしてそんな顔をするのか分からなかったし、その理由も知らなかった。
そして、仕事の束の間に何度「お休みください」と彼らが言っていただろう。その全てを、自分は「大丈夫だ」と軽く受け流してきた。
――――彼らの表情は、言葉は、心配の色を帯びてはいなかっただろうか。だからあんなにも言葉をつらねていたのではないだろうか。
それを、自分は無意識のうちに無碍にしてきたというのか。
突如として知ることとなってしまった事実に、愕然とする。
「心配なのだろう、世界に飛び立っていった彼らが」
やんわりとした口調とは裏腹に、その言葉は容赦なく心を貫いてくる。
……心配ではない、といえば嘘になる。無事ならばいい。怪我をして動けなくなっていたら。病気になって倒れていたら。危険な目にあっていたら。
……生命を、落としていたら。
心配は恐れとなり、毎日、アーヴィンを
けれども、それを口に出して言うのは、どうしてか憚られた。
口を閉ざしているアーヴィンに、なおも天空神は淡々と言葉を紡ぐ。
「ここにはお主を慕う者がたくさんおるだろうに。何故話をしない」
彼らはアーヴィンのことを心配しているのだと、言外に匂わせている。
「……」
この不安を、誰かに話すことができればきっと気持ちが楽になるだろうと思う。いつもならば、その話し相手は息子のクロスで、良き相談相手であった。
ただ、彼はもうこの里にはいない。必然的に、話す機会は失われてしまった。
かといって、他の誰かに話をして、何かが変わるとも思わなかった。
それに、なにより。
「上に立つ者が揺らいでいては、下の者に示しがつきません」
簡単に口に出せるようなものではない。
アーヴィンの確固たる言葉に、天空神の目元に険がはらんだ。
「強情だな。長老としての意地か?」
愚かな、と怒気をはらんだ叱責が耳に届く。
その声は今までに聞いたことがないほど怒りに満ちていて、突然のことにアーヴィンは思わず身をすくめた。
「お主が倒れれば、この里は支えを失う」
その言葉に、一瞬呼吸が止まった。
怒気をはらんだ眼差しは鋭く、強い。
「上に立つ者の意地? それは結構。大いに歓迎すべきことだ」
しかし、今回のことは別だ。
上に立つ者として、意志は強く持たなければいけない。クロスという族長がいなくなってしまった今、長老であるアーヴィンが里を統べていかなければいけない。
彼もまた、昔は族長として里を統べていた経験はある。けれども、多くの民が〈魂送り〉でいなくなってしまったこの里を、今までと同じように統べるのは――――守るのは、難しい。
――心に負った寂しさは、これから永い時をかけたとしても、彼らの中から消えることはないだろう。
「アーヴィン。この里にいる誰よりもお主の担う責は重い。なればこそ、お主しかいないのだ」
この里を守っていけるのは。
しん、と静まり返った室内で、息をするのも忘れてしまいそうになる。
改めて気付かされた長老としての責任。
「…………わたしは」
険しい表情を浮かべていた天空神が、一転して顔をほころばせた。
「……ここの者がな、あれやこれや術を使って我に接触してきたのだよ」
その告白に、アーヴィンは目を見開いた。
こうして何度も神と対話しているアーヴィンにとっては慣れてしまったものではあるが、実際、天界に住まう神が下界に降りてくることは滅多にない。
まして、生物の住まう地に訪れることは、よほどのことがない限りありはしないのだ。
「いやはや、恐れ入るよ」
神を喚ぶ術が無いわけではない。
しかし、それには膨大な知識と下準備が必要であり、なおかつ成功するとは限らない。失敗すれば神を呼ぶことはおろか、その術の反動で昏睡状態に陥ってしまうこともあるという。
その術を知る者は少ない。だが、その術を記した本はどこかにあったはずだ。この屋敷には書物を集めた部屋がある。
きっと彼らは、そこで術を見つけたのだろう。
「どうにか休ませる方法はないかと、泣きつかれてな」
しかし、まさかそんな事態になっていたとは知らなかった。
くつくつと笑いを噛みしめている天空神に、アーヴィンはますます居心地が悪くなってきた。
逃げ出したくなる衝動をおさえて、気持ちを落ち着けるために腕を組む。
「それで、この薬酒を?」
確認の意味での問いかけだが、返答は分かりきっていた。
案の定、天空神は首を縦に振った。
「我が愛する鳥たちの頼みを、無碍にできまい?」
神は自由だ。それでいて傲慢で、気まぐれで、そして下界の者の思惑には乗らない。
けれど、この神は。
「……全く、どうしたものか」
情愛を秘めた優しい瞳が、物語っている。
強ばっていた体から力が抜けていき、無意識のうちにほっと安堵の息を吐き出していた。
きっとこの神は、これからもずっとこの里で生きる者を、〈渡り鳥〉たちのことを、ただひたすら愛してくれるのだろう。
だからこそ、その思いには思いを返していかなければいけない。
――そして、こんなことをしでかしてくれた彼らにも。
「こちらはありがたく頂きますよ、ロスト=フィア神。薬師神にも、感謝しますとお伝え願えますか?」
神の温情を無碍にはできない。
居住まいを正してアーヴィンが頭を下げると、是と答える声が聞こえた。
「伝えよう」
そう言うと、天空神はかたんと音を立てて椅子を引いて立ち上がった。
「行かれますか?」
問いかけながら、アーヴィンも一緒に立ち上がる。
「我の用事は済んだからな」
しかし、天空神は部屋の唯一の出入り口となる扉へ向かわずに、アーヴィンの方へと足を進めた。
どうしたのだろうと眺めていると、彼の横を通り過ぎて窓の格子に手を添えた。
――帰りは、そこから行くのか。
来た時と同じように玄関から…………いや、それはそれで大変なことになりそうな気がする。やはり、窓から出ていった方が安心か。
「ああ、それと」
鍵を外して窓を開けた。すっと入ってきた風が、二人の髪を揺らす。
天空神は振り返り、アーヴィンを見た。また何か怒られるのだろうかと、とっさに身構えてしまう。
「次、このようなことがあった場合には薬師神ではなく
少し強い口調で言われたそれに、しかしアーヴィンは首を傾げた。
「微睡神……?」
聞いたことのない神の名。
アーヴィンが疑問符を浮かべていると、天空神がそういえば、とこぼす。
「下界ではあまり名を知られていないんだったな」
伝承や神話といった知識は、ある程度持ち合わせているつもりではあったのだが、知らない名前が出てくる辺り、まだまだ知らないことの方が多そうだ。
アーヴィンは天空神の言葉の続きを待った。
「微睡神は水と眠りを司る神。あれは常に眠りを促す小枝を携えていて、それに少しでも触れただけで深い眠りに誘われる」
その効力は数日の間続くという。効力を強めれば、永遠の眠りについてしまうこともあるそうだ。
それを聞いて、アーヴィンはひくりと頬をひくつかせた。
「我が言いたいことは、分かるであろう?」
天空神は悪戯っぽく口角を上げた。
――つまり、実力行使ということだろう。
「……心得ておきます」
アーヴィンは苦笑いを浮かべるしかない。
そんな彼の返答に天空神は軽く微笑むと、目をつぶった。ふわりと目に見えぬ不可思議な風が、彼の全身にまとわりついていく。
「次に会う時には、もっとましな顔をしているように」
その一言を最後に、天空神の姿が風に溶ける。
そして、次の瞬間には窓の外に白い巨鳥の姿があった。重さを感じさせない動きで、どんどん空高く羽ばたいていく。
「…………」
天空神を見送ったアーヴィンは、ゆっくりと窓を閉めた。
静けさが舞い戻ってくる。
「………………さて、と」
窓に背を向けて、先ほどまで座っていた椅子に再び腰を下ろした。
「やはり、皆に謝ってこなければなるまいなぁ……」
これは自身で解決していかなければいけない問題だった。だからこそ、誰にも相談なんてできるはずもなかった。
その思いが不安を募らせ、周りに気取られるほどに膨張し、そしてこの事態に陥った。
……これまでは、なんだかんだと話し相手になる息子がいたから、平静を保つことができていたのだろうか。
「あいつ、どうしてるんだろうな……」
ふと、その息子と、息子のペアとなった少女を思い浮かべた。
まがりなりにも、息子は自分と近しい存在と〈魂送り〉をすることになってしまったのだ。心情は朗らかではないだろう。
そう思ったのだが……はて、果たしてそうだろうか。
「……いや、逆に安心する、か?」
もしも彼が相手でなければ、彼女はどこの誰とも知れぬ者と一緒に行動することになる。里の者を疑うわけではないが……やはり、心配なものは心配だろう。
だったら、目の届くところにいてくれた方が安心できるというものだ。
つらつらと他愛もないことを考えていたアーヴィンだったが、ふと視界の隅に入ってきた物の存在に気付き、現実に引き戻された。
「……どうするべきか」
天空神が置いていった薬酒。
ああ言ってしまった手前、飲まないという選択はすでに無い。
後で飲むという選択肢もあったが、もしも飲むのを忘れてしまった時が、怖い。記憶力に自信はあるが、万が一ということもある。それに、飲む前に天空神がまたここを訪れては一大事だ。
――つまり、今、飲むしかない。
「まあ、酒精はそんなに入っていないと言っていたしな……」
少しだけなら、大丈夫だろう。
そう結論づけて、アーヴィンは包みに入っていた杯を取り出した。徳利の封を外すと、ゆっくりと斜めに傾ける。
とくとくと注がれる液体の色は無色透明。これで、変な色をしていたら飲むのを躊躇ったのだが……存外、普通のもので拍子抜けしてしまった。
薬酒を注ぎ終えると徳利に封をし、杯を手に取った。すると、甘い果実のような匂いがふわりと鼻孔をくすぐった。
甘い薬酒なのだろうか。薬と聞いて、苦いものだろうと考えていたのだが。案外、飲みやすいものを持ってきたのだろうか。
そんな軽い気持ちで薬酒をあおったのがいけなかった。
「…………っ!?」
舌から脳髄に駆け上がった衝撃に、アーヴィンは持っていた杯を落とした。
からん、と音を立てて、しかし杯は割れることはなく、机の上でひっくり返る。
すかさず口元を手で押さえたのは、半ば反射にも近い。
「にっがい」
かろうじて、薬酒を吐き出すことは防いだ。
なんという苦さだ。これまでに経験したことのない味に、舌はまだ痺れている。『良薬は口に苦し』という言葉を聞いたことはあるが、限度というものがあるだろう。
ごくり、と何とか液体を飲み干したものの、苦みはまだ口の中に居座り続けている。
思わず力が抜けて机に突っ伏したアーヴィンは、口の中の違和感が消えるまでは動くのを諦めた。口の中をすすぎたい気持ちではあるが、それの為に動くのさえも億劫に感じられた。
それが薬のせいなのかは、定かではない。
――そして、頃合いを見計らって部屋に入ってきた側仕えが机に突っ伏しているアーヴィンを見つけた途端、倒れていると勘違いして慌てて駆け寄るのは、もう少し後の出来事である。