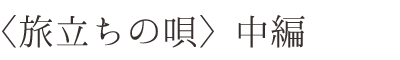命の輪廻に刻まれた鳥たちの〈
□ ■ □
集会が始まる数時間前。クロスは一人廊下を歩いていた。
彼がいるのは、この里の中でも一番大きい白い建物。外側も内側も白い煉瓦で作られたここは、大きいのでそれなりに目立つ。
さらに、この建物には鐘があった。渡り廊下の先にある、これもまた白い煉瓦で造られた塔の天井に吊り下げられている。時刻を報せるために朝、昼、夕方に二回ずつ鳴らす。また、月に何回かある集会でも、始まりの合図として鐘を三回鳴らす決まりになっていた。
「族長」
背後からかけられた声に、クロスは振り返った。
そこにいたのは召使いの男だった。何名かいる召使いでも、伝達係として走り回っている姿を見かける。
今回も、何かの伝言だろうか。
「どうした?」
クロスが問いかけると、男は軽く会釈すると口を開いた。
「長老がお呼びです。すぐに
「分かった。ありがとう」
片手を上げて、下がっていいぞと男に合図を送る。
彼はまた会釈すると、機敏な動きでその場を去っていった。
それを見送ったクロスは、顎に手をそえる。何の用事があるのだろうと思案しながら、指定された白鳥の部屋へと足を進めた。白鳥の部屋はこの建物内でも奥にある。長老の書斎を兼ねており、滅多なことではあまり人は近づかなかった。
一つ角を曲がり、部屋の扉に記された鳥の模様の色を確認していく。青……黄色……白。ここだ。
部屋に入る前に、身だしなみを整える。一呼吸おいてから、扉を二度叩いた。
「父上、お呼びですか?」
部屋の扉を開けて中に入ると、窓際に近いところにある椅子に男は座っていた。少し寂れたような黄土色の髪に、濃い紫の瞳。長老であり、クロスの父でもあるアーヴィンは悠然と構えていた。机の上には幾つかの羊皮紙と、花が飾られた花瓶が置かれていた。
「来たか」
「……ほぉ、こいつが」
長老の言葉の後に続いた見知らぬ声に、クロスはハッとして辺りを見渡した。そして、その声の主を見つける。
窓辺にたたずむ影があった。流れる髪はきらめく白銀。二つの瞳は閉じられていて、腕を組み、壁に背を預けて立っていた。
「父上、彼は誰ですか?」
クロスの問いかけにアーヴィンはちらりと白銀の男を横目で見やる。
「天空の神……ロスト=フィア」
彼の言葉に、クロスは目を丸くした。驚きの表情を隠せない彼を見て、白銀の男――天空神は淡く微笑んだ。
「天空神の姿は鳥だとお聞きしましたが……」
天空を司るロスト=フィア神は、天駆ける白い巨鳥であると、伝説では伝えられている。その白さはさながら雪原の如く。体躯を覆う羽根は光に当たると白い燐光を放つそうだ。
しかし、今目の前にいるのは十七くらいの華奢な青年。
「我の正体は鳥。今のこの姿は仮のものだ」
「……あぁ、なるほど」
鳥の姿でこの場所に訪れれば、きっと大事が起こる。そのことを見越して人の姿で現れたのだろう。
クロスはそう納得して、表情を堅くした。
「それで?」
「……それで、とは?」
天空神は閉じていた瞼を持ち上げた。覗くのは空のように透き通った蒼い双眸。その二つの蒼が、クロスを射抜く。
「なぜ、天空神が地界におられるのですか?」
神の名を持つ者は天界と呼ばれる場所に暮らしている。そこは空の上にあると云われているが、地界の生き物がその場所に行くことはできない。そもそも、空のどこに在るのかさえ分かってはいないのだ。
天界には神が住まう。常に地界の流れを見届け、ただその歴史を記すのみ。
その神が、地界に降りてきたのだ。何かがあったとしか思えない。
「天界にいるのが飽きた」
そんなクロスの思惑も何もかもを吹き飛ばすような、簡潔な一言。
「……はぁっ!?」
その一言にクロスはこれ以上ないほど目を見張った。
飽きた、とはどういうことだ。
そんなクロスの表情を見て、天空神が吹き出した。
「嘘だ。ははっ、今の族長は生真面目で面白いな」
笑いながら言う彼の姿は、どこか子供のように見えた。しかし驚きの余韻がまだ続いていて、彼の言葉を理解するのに少々時間が必要だった。うそ、嘘。
視線を巡らせれば、アーヴィンはというと口元を手で押さえていた。けれど肩を振るわせていて、声を押し殺しているのが分かった。これは絶対に笑っている。
これは、からかわれたということだろうか。口の端がひきつるのが分かる。
「ち、父上……」
「悪い。おまえはそういう奴だったよ」
それは、どちらのことを指しているのか。
「まあ、茶番はこれぐらいにしておこう」
ふと、天空神が今まで浮かべていた笑顔を消した。一変して、表情が真面目なそれに変わる。
思わず、クロスは身構えてしまった。
「君たち……いや、〈渡り鳥〉には、〈
静かに、穏やかに、しかし神は力強く言った。
聞きなれない単語に、クロスは眉を寄せる。
「……やはり、そうか」
アーヴィンのささやくように言った一言。クロスと天空神はほぼ同時に彼へ視線を向けた。
アーヴィンは両の手を組み、その上に顎を乗せて瞼を閉じていた。何かを思っているような雰囲気。それは、どこか寂しさを感じさせた。
「父上、それはどういう意味ですか?」
アーヴィンは、ゆっくりとその瞼を持ち上げる。視線をクロスに向けて、そのまま流れるように天空神を睨みつけるように見た。
「自分の時もそうだったからさ。なあ、ロスト=フィア神?」
「そうだな」
長老の問いかけに、天空神は是と答えた。
「昔……まだ、我々は名も無き民であった。この島で静かに暮らしていた時に、貴方が天界からやって来た」
「我はその民に名を与えた。〈渡り鳥〉という……〈
アーヴィンの言葉を引き継ぎ、天空神が言う。
「〈界を巡る者〉?」
「天界に住まう白き鳥の名だ。我の従者でもあり、その名の通り、天界と地界を巡っている」
クロスは額に指を当てて、二人の言葉を頭の中で整理する。――〈渡り鳥〉の名は、族長になった時に聞いたことがあった。けれど、天空神が最初に言った言葉が、分からない。
「〈魂送り〉というのは何ですか?」
クロスは天空神をじっと見つめる。彼はクロスを見返し、けれどどこか遠くを見ているようだった。
「地界の生き物はいずれ死にゆく存在。死した者の肉体は大地に還り、魂は天に還る」
そこで彼は一度区切った。天空神は無表情で、彼が今何を思って言葉を紡いでいるのか感じることはできない。
クロスは静かに聞いていることしかできなかった。
「だが、この地界には、様々な要因で天に還れない彷徨う〈魂〉がいるのだ。己が死んだことに気づかぬ者、この地界に未練がある者……その〈魂〉を、還り
感情の奥に隠された悲哀を感じた気がした。
クロスは何かを言おうとして口を開いたが、言葉になることはなかった。何を言えばいいのかわからない、というのが正しいだろうか。
天空神の思惑がどこにあるのかはわからない。
それでも何かを言わなければいけないという義務めいた何かが、クロスの口を動かした。
「……どうやって、その〈魂〉を天に送るのです?」
「君たちは一人ひとり楽器を持っているはずだ」
多くを語らずに、重要な言葉だけを並べる神。それを聞き、クロスは再び考え込む。
楽器、というと確かに持っている。生まれた時より己と共にある存在。それは命と同等の価値のあるもの。
――――……そういえば、今は代々族長にのみ継承される楽器を持っていたな。
そこで、過去の出来事が脳裏をよぎった。はっとしてクロスはアーヴィンの方へ顔を向ける。顔を見、その視線は最終的に彼の右翼に止まった。
「まさか、あの日も〈魂送り〉を……?」
クロスの言葉に、アーヴィンは苦笑いを浮かべた。
「そうだな。〈魂送り〉は里の中でも機密事項。それを知るものは、私の代で〈魂送り〉に参加した者のみ……とは言っても、誰も喋りはせんがな」
「あれは十四、五年前になるか」
「そうですね……もう、そんなになりますか」
過去に〈魂送り〉が行われたのは、もう何十年も前のこと。当時、族長だったのはアーヴィンだった。
けれど、それが行われたのはたったの一ヶ月ほど。
「思い出したくもないことです」
一ヶ月という短い期間で終わってしまったのには、アーヴィンの不慮の事故があったからだ。彼が空を翔ている時、彼を鳥と勘違いした猟師の発砲した弾が右翼に当たったのだ。落下し、さらには地面にその右翼を強く叩きつけてしまった為に、翼の付け根の部分がねじ曲がってしまった。
――そして、アーヴィンは再び空を飛ぶことができなくなってしまったのだ。
その当時、アーヴィンはまだ若かったクロスに族長の座を譲り〈魂送り〉を続けようとしたことがあった。必死になって己のことを呼ぶ息子を、アーヴィンは苦しい思いで見ていた。この幼い子を、巻き込んでしまう。けれど〈魂送り〉は続けなければいけない。〈
だが、そこに天空神が現れた。「無理をしなくていい」と、厳かに言ったことを、アーヴィンは未だ忘れられない。
「あの時は貴方にこの翼の傷を治していただいたんでしたな」
「そういえば、そうだったな」
それにしても、と天空神は続ける。
「あの日、お主を運ぶのに苦労したな。あまりにも暴れるものだから、思わず手がでてしまったよ」
あの時はアーヴィンも混乱していた。傷ついた翼。抗えない〈宿命〉。狼狽している息子。その全てをどうにかしなくてはいけないという義務感で、ほぼ正気を失っていた。
「はっはっは、そうでしたな。あの時、まさか神に殴られて気絶させられるとは思わなかった。鳩尾に入ったから、余計に効いた」
今でこそ笑い話になっているが、当時としては笑い事では済まされなかった。
それほどまでに緊迫した時だったのだ。
「え……それじゃあ、あの日の男はロスト=フィア神だったのですか!? でも、俺が見たのは……」
「クロス、天空神の本来の姿は鳥だと言っただろう。人の姿になるのは我々の前だけであって、その人の姿も様々だ」
クロスの驚きように、アーヴィンと天空神は揃って苦笑を浮かべた。
そう、あの日見た人をクロスは覚えている。しかし、それは目の前にいる男ではなかったはずだ。
「一人だとつまらないからな。いろいろな人間を観察して、気に入った人間の姿に変えている。この姿は何人目だったか……んー、忘れてしまったなぁ」
神でも、そういうことをするのか。クロスは思わず感嘆してしまった。
「して、翼はどうだ?」
「動かせないのは辛いが……まぁ、大丈夫です」
言葉に合わせて、アーヴィンが意識して左翼を動かす。同じように右翼を動かそうとするも、怪我の影響からか思うように動かなかった。
「そうか」
「……貴方は」
そこで、アーヴィンの表情が一転した。
「また、同じことを繰り返すつもりですか!?」
〈魂送り〉は、翼を持つ彼らにとって危険なことであった。空を翔れば鳥と間違えられることもある。最悪、命を落とすこともあるだろう。
「私は老いた。翼を使うことも少ない……だが、これからの〈渡り鳥〉はほとんどが若者だ! 彼らに――」
「それが〈渡り鳥〉という名を受けた者の〈宿命〉だ」
アーヴィンの激昂を、天空神は涼やかな表情で受け流し、強く言い放った。厳かなその言葉に、アーヴィンは言い返せない。
彼の言葉は、神の言葉は絶対である。否と答えることは、できない。そして、その〈宿命〉の言霊は、昔より彼ら〈渡り鳥〉に深く刻みつけられてきていた。
〈魂〉とも呼ぶべき部分が、すでにその事実を受け入れていた。拒絶することは、きっとできないのかもしれない。
「……〈宿命〉は、変えられないのですか」
願わくば、何も起こらないことを望む。たとえそれが無駄なことだとわかっていても、願わずにはいられないのだ。
「無理だな。〈宿命〉は永劫に続き、抗うことはできない」
アーヴィンは打ちひしがれる。己と同じことが起こらなければと、そう願うしかないのだろうか。
「だが」
天空神は二人を見た。クロスも、アーヴィンも真剣な顔つきで見返してくる。その表情が似ているのは、さすが親子だからか。
「我の言葉を風に乗せて民に聞かせるといい。一度だけだが、その身を守るものとなるであろう」
アーヴィンはその言葉に瞠目した。神は気まぐれである。気高く、尊ぶべき存在で、何ものにも縛られない。けれど、時としてそれが当てはまらないときもある。
気まぐれであるが故に、この天空神は、崇拝してくれている者たちを愛している。その愛すべき民を守るために、力を貸すというのだ。
同じことを、繰り返さないために。
「……分かりました。日時はいつですか?」
クロスの言葉に、アーヴィンは驚きの表情を見せた。が、それも一瞬ことですぐに表情を元に戻す。口を挟まず、ただ二人の会話に耳を傾けた。
「七日後の暁の
七日後。それは長いようで、短い時間。
「それでは、その前日の黄昏の刻に〈旅立ちの儀〉を行うとしようか」
「そうだな」
「〈旅立ちの儀〉……?」
初めて聞く単語に、クロスは首を傾げた。
「〈渡り鳥〉として、この里にいられるのはその日が最後だ。例外もあるが、一度出てしまえば、この里に戻ってくることはない」
つまり、〈渡り鳥〉はこの里に戻ってくることなく、その一生を外の世界で過ごすこととなる。
何もかもをこの場所に置いて、〈宿命〉に縛られた鳥は空を飛ぶしかない。
「それを知るのもまた族長のみなのだがな。……その〈渡り鳥〉たちを讃えるために行うもの、それが〈旅立ちの儀〉」
「何をするんですか?」
クロスの質問に、アーヴィンはふむと考える。
「前は族長の私が言葉を紡ぎ、唄を唄ったが……今回は神の言葉を唄うことになるか」
「そうだな。唄の言葉は我が考えておく」
とんとん拍子で進んでいく会話に、クロスは思わず唸った。つまりは、現族長である己が唄わなければいけないということか。……あまり唄は得意ではないのだが。
焦りと緊張が脳内をかけ巡る中、控えめなノック音がその部屋に響いた。一息の間を置いて、扉が開かれた。
クロスはゆるりと顔をそちらに巡らせる。
「失礼します。クロスは……あら、その方は……?」
浅葱色の長い髪、深い緑色の双眸。たおやかな雰囲気を漂わせる女性が中に入ってきた。
「エステル?」
「こちらにいらしてたのね、クロス。ところでそちらの方はどなた?」
「ああ、彼は天空神ロスト=フィア。……紹介します、妻のエステルです」
クロスの紹介に、エステルは深々と頭を下げた。
「天空神、お初にお目にかかります」
「ほぅ……これは」
感嘆。天空神はエステルに近づいた。皆が彼の行動に疑問符を浮かべる。
「あの、何か?」
「良き声を持っているな。高く澄んだ、麗しい鳥のような声だ」
「まあ、ありがとうございます」
天空神の誉め言葉に、エステルは笑みを浮かべた。
「それにその美貌……どうだ、我の妻にならぬか?」
彼女の手をとり、手の甲に口づけを落とす。天空神の突然の行動に、エステルは目をぱちりと瞬かせた。驚いたまま固まってしまった彼女に、思わず口の端が上がる。
「えっ」
そして、それ以上に驚きを隠せなかったのはクロスだった。
「ふふ、光栄ですわ」
驚きから一転、エステルは自分の手に添えられた天空神の手を握り返すと満面の笑みを浮かべた。柔らかくほのかに甘い雰囲気を漂わせる二人に、クロスは何もできずに立ち尽くしていた。
それを傍らで見ていたアーヴィンは、どうしたものかと苦笑いをするしかなかった。
「ですが、もう人妻ですので遠慮しておきます」
そう言って、エステルは天空神から離れてクロスの隣に立った。彼の手を取り、にっこりと笑む。
「え、え……?」
「そうか、それは残念だな」
二人の流れるような会話。そして、こちらを見る視線を受けて、クロスはようやっと理解した。……この二人に、言葉巧みに遊ばれていたのだ。
そうと気づくと、張りつめていた緊張感がどっと消えた。不安が安堵に変わり、頬がゆるむ。冗談だと分かった今でも、先ほどのことは心臓に悪かった。
そんなクロスの内心を察してか、エステルは小さく「ごめんね」と言った。
「天界にも貴女のような方がいるといいんだがな……と、その話は置いとくとして」
そこで区切り、天空神はエステルを見た。
クロスとアーヴィンも、彼の視線を辿って彼女を見る。
視線の先にいるエステルは、何だろうと首を傾げた。
「これで唄姫は決まりだな」
一拍の間。
「ん?」
「は?」
「え?」
三人の声が同時に上がった。神の言っている意味が、理解できるまで少しの時間が必要だった。
最初に、その言葉の意味に気づいたのはアーヴィンで、何とも言えない表情をつくった。
「天空神よ、本人に了承も得ずに決めるのはいかがなものかと」
「……それもそうか。姫よ、どうだろうか?」
「お話が見えないのですが……」
そういえば、彼女が部屋に入ってきた時には、話はあらかた終わっていたのだった。天空神が言っていたことも、今問いかけていることも分からないはずだ。
クロスはこれまでの話をエステルに簡潔に伝えた。彼女は少し考えた後に、頷いた。
「私でよければ、唄いましょう」
「では、決まりだな」
ここから全てがはじまった。
後に、皆が別れたる道を選ぶことになることを、今はまだ知らない。